広告 ※当サイトではアフィリエイト広告を掲載しています
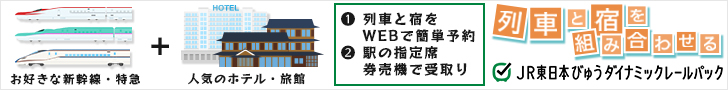
国鉄は1949年に公社として設立され、高度経済成長期を通じモータリゼーションの急速な進展などにより、それまでの国鉄中心の輸送構造に大きな変化が生じました。しかしながら、戦時中の酷使による疲弊に加えて設備投資に立ち遅れ、戦後の高度経済成長期における輸送需要に対応出来なかったため、輸送力増強と蒸気機関車牽引列車の置き換えによる輸送方式の近代化を図り、経営収支の改善を図ろうとしました。幹線の複線化と電化、新線の建設、新製車両の導入、特急列車の増発、リゾート列車の運転など増収に向けた施策を行ったものの、国鉄の赤字は雪だるま式に膨らみ社会問題となり、1982年度に1日あたりの赤字額が57億円に膨らみ、破産状況を迎えてしまいました。
経営状況を改善するために国鉄当局は業務の見直しを計画しましたが、これに反対した労働組合は何度もストライキを決行したため鉄道離れに拍車が掛かり、貨物輸送が大幅に減少し荷物輸送と郵便輸送が廃止となり、利用者が少ない地方交通線の廃止が行われました。1986年11月に国鉄改革関連8法案が国会で可決され、効果的で地域の実情に即した経営が出来る経営形態に改めた上で国鉄を再生するために、JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州の旅客鉄道会社1社とJR貨物の貨物鉄道会社1社に分割民営化されることとなり、1987年3月31日に国の運営による鉄道としての役目を終えました。
国鉄分割民営化により民間の鉄道会社となった国鉄は1987年4月1日にJRグループとして発足し大手私鉄型の鉄道会社になりました。国鉄時代は制約があった関連事業は幅広い分野への進出が可能となり、輸送サービスが向上し旅客鉄道会社6社と貨物鉄道会社1社に分割されたので、運営形態に個性が見られるようになりました。
国鉄分割民営化から先月の31日で36年が経ちましたが、設備や旅客営業制度に国鉄の名残が今でも残っており、国鉄分割民営化は鉄道の歴史における大きな転換点になりました。
広告 ※当サイトではアフィリエイト広告を掲載しています
参考文献
車掌の仕事 田中和夫(元札幌車掌区車掌長)北海道新聞社2009年10月1日発行
「もし JRが分割されていなかったら」岩成政和 鉄道ジャーナル2022年11月号株式会社鉄道ジャーナル社2022年11月1日発行
